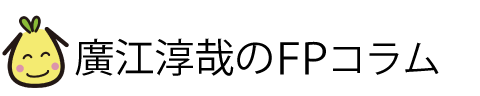今回は、法改正がありました令和4年からの住宅ローン控除についてお伝えします。
そもそも住宅ローン控除というのは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいますが、個人の方が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、その人自身が住み、その取得した住宅やその人の収入等が一定の要件を満たしている場合に、その住宅ローン等の年末残高に対して、一定の割合を住んだ年以降の各年分の所得税額から控除してくれるものです。
簡易に説明するなら、住宅を取得した際に一定の要件を満たしたら、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する額が所得税等から一定の期間戻ってくる、減税になりますよというものです。
その住宅ローン控除に法改正があり、令和4年から一部内容が変わりましたので、ご説明していきます。
6つの改正ポイント
改正ポイントとして、6つのトピックスでお伝えしていきます。
「①控除率」、「②控除期間」、「③住宅の種類による借入限度額」、「④住宅ローン控除を利用する人の収入要件」「⑤収入要件に伴う住宅要件緩和」、「⑥住民税からの住宅ローン控除」の6つです。
①控除率
まず大きな改正ポイントとなる「控除率」ですが、改正により引き下げになりました。
令和3年までに住宅を取得された方は、住宅ローン年末残高の1%が所得税などで戻ってきたのですが、改正により令和4年以降に住宅を取得された方は「0.7%」となります。
仮に、年末の残高が3,000万円だったら、1%だと30万円の住宅ローン控除が受けられていたのが、0.7%ですので21万円となります。
この控除率引き下げの背景は、住宅ローンの金利が非常に低い状態が続いているからです。
例えば、住宅ローンの金利が0.5%で、住宅ローン控除が1%だと、住宅ローン控除で戻ってくる金額の方が住宅ローンの払う利息以上になるということが起きていたんですね。
税金が戻ってくるから、多く借りた方がお得・・・みたいな状態ですね。
これを是正するために、住宅ローン控除をこれから利用する人にとっては残念な改正になりますが、控除率が引き下げられました。
なお、ファイナンシャルプランナーとしては、この控除率引き下げにより、毎年受けられる控除額が少なくなりますので、これを契機に、共働き世帯は、夫婦で住宅ローン控除を受けるという方が益々多くなるのかなぁと想像しています。
この共働き世帯の「夫婦で住宅ローン控除」については、メリットや注意点等、改めてお伝えしたいと思っています。
②控除期間
続いての改正ポイント2つ目は「控除期間」で、新築住宅等は「13年」になりました。
昨年までも一定の要件を満たしたら、控除期間13年というケースもありましたが、11年目~13年目までは住宅価格の2%を3で割った金額が各年の控除上限とか、細かな規定があり、少しややこしかったです。
それが1年目から13年目まで同じ計算式で控除額が出せるようになりましたので、ファイナンシャルプランナーとしてはスッキリとした制度になったなぁという印象を持っています。
ただ、どんな住宅取得でも控除期間が13年ではなく、住宅の種類や居住年によって、13年の場合と10年の場合があるので、その点には注意が必要です。
なお、改正ポイント3つ目の「住宅の種類による借入限度額」も踏まえまして、次のような表をご用意しましたので、控除期間13年か10年かの確認をしてください。
③住宅の種類による借入限度額

上は新築住宅、下は既存住宅、いわゆる中古住宅の場合です。
上の新築住宅ですと、認定住宅(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅)の場合ですと、居住年が令和4年または5年ですと、借入限度額5,000万円までが住宅ローン控除の対象となり、令和6年・7年に居住した場合ですと4,500万円までが住宅ローン控除の対象となります。控除期間は13年ですね。
また、ZEH水準と書いてありますが、ゼッチと呼んだりするネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのことで、高い断熱性能や太陽光発電や蓄電池などの設備により、経済性・快適健康性、災害等の非常時も安心な住宅のことです。
このZEH水準省エネ住宅に居住される場合は、居住年が令和4年または5年ですと、借入限度額4,500万円までが住宅ローン控除の対象となり、令和6年・7年に居住した場合ですと3,500万円までが住宅ローン控除の対象となり、控除期間は13年です。
続いて、省エネ基準の適合住宅に居住される場合は、居住年が令和4年または5年ですと、借入限度額4,000万円までが住宅ローン控除の対象となり、令和6年・7年に居住した場合ですと3,000万円までが住宅ローン控除の対象となり、控除期間は13年です。
そして、それらの省エネ基準を満たさない新築住宅に居住する場合は、令和4年または5年ですと、借入限度額3,000万円までが住宅ローン控除の対象となり、令和6年・7年に居住した場合ですと2,000万円までが住宅ローン控除の対象となります。
ただ、省エネ基準を満たさない新築住宅の控除期間ですが、令和4年と5年に居住する場合は13年であるのに対し、令和6年以降に居住する場合は控除期間が10年になる点はご留意ください。
家の種類によって住宅ローン控除対象となる借入限度額が変わったり、控除期間が変わったりしますが、この表を見ていると、国の方針として、環境問題やエネルギー問題の観点から「省エネ住宅」を優遇していくという方針が見えますね。
続きまして、下段は既存住宅の住宅ローン控除についてです。

ここでのポイントは控除期間ですね。居住年に関わらず、13年ではなく、10年になるというのが新築住宅との違いですので、ご確認ください。
なお、こちらの表で「居住年」と書いていますが、令和4年以降に新たな住宅に住まれる方が今回ご説明の住宅ローン控除の対象となります。
既に令和3年までに新居に居住を開始されている方は、以前の住宅ローン控除の制度が対象となる点もお伝えしておきます。
④住宅ローン控除を利用する人の収入の要件
改正ポイント4つ目は「住宅ローン控除を利用する人の収入の要件」についてです。
令和3年までは、合計所得金額3,000万円以下でしたが、2,000万円以下になりました。
ここで言う「合計所得金額」というのは、例えば、会社員の方で会社からもらう「給与」以外に、副業で個人事業として収入があればその事業所得も、不動産収入があればその不動産所得も合わせて計算するということです。
さらに、「収入」ではなく、「所得」というのもポイントです。聞きなれない言葉かもしれませんが、「所得」というのは税金を計算する時に使われる言葉で、経費や控除を差し引いた後の金額のことを言います。
会社からの給与だと、給与所得控除という一定の控除を差し引いた後の金額が「給与所得」となります。
ちなみに、給与収入が年間850万円を超えますと、給与所得控除は一律で195万円となりますので、もし会社員の方で、収入は会社からの給与のみという場合でしたら、合計所得金額が2,000万円以下になる方というのは、給与収入が2,195万円以下の方と言えます。
⑤収入要件に伴う住宅要件緩和
続いて、「収入要件に伴う住宅要件緩和」についてです。
こちらは合計所得金額が1,000万円以下の方限定となり、さらに令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅を取得する場合に限られますが、住宅ローン控除を受けるための住宅要件のうち、床面積要件が40㎡以上に緩和されます。
住宅ローン控除を利用するための住宅要件の床面積は基本的には50㎡以上なのですが、それが40㎡以上まで緩和されますので、比較的小規模の住宅取得にも住宅ローン控除が利用できるということです。
利用できる人の収入要件、建築確認の期日にはご留意ください。
⑥住民税からの住宅ローン控除
最後に「住民税からの住宅ローン控除」についてもお伝えします。
所得税額で住宅ローン控除を受けきれなかった場合は、その額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)までの範囲で住民税からも住宅ローン控除をしてもらえます。
なお、令和3年までは消費税増税の激変緩和のため、特例的に課税総所得金額の7%(最大136,500円)まで、住宅ローン控除が所得税から受けられなかった分を住民税から受けられていました。
それが、令和4年以降は元に戻り、所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)までとなります。
ということで、本日は、法改正された令和4年以降の住宅ローン控除のポイントについてお話してきました。
これから住宅を取得される方は、是非ご参考になさってください。